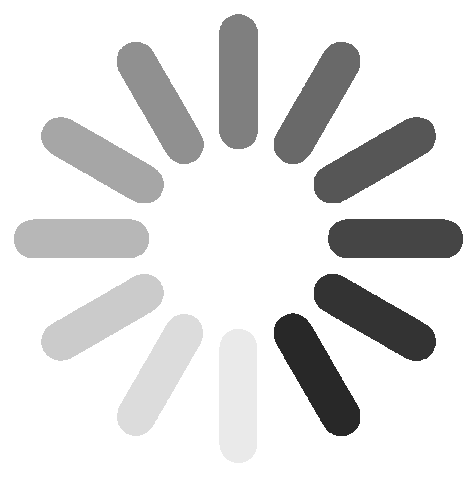Dim
勤労者が妊娠した場合、子供を出産する前後に出産前後休暇を取る。また、満8歳以下の小学校2 年生以下の子供を養育するために育児休暇(育児期勤労時間短縮)制度を利用することもできる。
- 育児休暇の場合は、妊娠中の女性労働者を含む
01出産前後休暇
(1)適用対象
- 勤労基準法上、1人以上の労働者を使用する事業場に従事する女性労働者は、労働契約の形態(正社員、非正社員など)に関わらず、誰でも使用することができる。
(2) 出産前後休暇の期間
赤ちゃんの分娩が正常に進むと、出産日を前後して90日間の休暇を使える。
出産休暇期間は、産後必ず45日以上でなければならない。
- ① 勤労者が流産・死産の経験がある場合、②勤労者の年齢が満40歳以上である場合、③勤労者が流産・死産の 危険があるという医療機関の診断書を提出した場合には出産前に使用できる44日の休暇を妊娠初期にあらか じめ使える。
産前及び産後休暇は当該事業場に勤務中の勤労者を対象とする制度であるため、休暇期間中 に勤労契約が満了する場合は、契約満了時点で産前及び産後休暇も終了する。
- 一度に二児以上(双生児など)を出産する場合、120日の出産前後休暇を受ける。この時、産後の期間は60日 間以上でなければならない。
(3) 出産前後休暇給付
- 出産前後休暇期間中に出産前後休暇給付が支給される。
- 大手企業の場合、60日分は会社で通常賃金の100%を支給し、残りの30日分は雇用保険で支 給する(月210万ウォン限度)。
- 優先支援対象企業(中小企業)の場合、90日間の休暇給付を雇用保険が支給し(月210万ウォ ン限度)、最初の60日分は企業が通常賃金と出産前後休暇給付の差額の分を支給する。
- 期間制・派遣労働者が出産休暇中に契約満了となった場合は、雇用保険から残りの休暇期間に対する法定休暇給付の支給を受けることができる。
- 一度に二児以上(双生児など)を出産する場合、大手企業の場合は75日分は企業が通常賃金の100%を支給し、 残りの45日分は雇用保険が支給する(月210万ウォン限度)。中小企業の場合、120日分に対して雇用保険が出 産前後休暇の給付を支給する(月210万ウォン限度)。
(4)出産前後休暇給付の申請方法
育児期の勤労時間短縮給付を受けようと思う勤労者は事業主から育児期の勤労時間短縮確認 書の発給を受けて育児期の勤労時間短縮給付申請書と一緒に申請人の居住地または事業所所 在地を管轄する雇用センターに提出する。
必要な書類
- 会社から受け取る書類:育児期の勤労時間短縮確認書、賃金台帳、勤労契約書の写しなど賃金 を確認できる書類
- 雇用労働部のホームページや雇用センターから受け取る書類:育児期の勤労時間短縮給付申請書
02流産・死産休暇
(1)適用対象
- 流産・死産休暇は、原則として自然流産の場合にのみ付与され(人工妊娠中絶手術の場合、「母子保健法」第14条第1項による場合にのみ付与)、休暇期間は妊娠期間に応じて付与される。
- 勤労基準法上1人以上勤労者を使用する事業場に従事する女性勤労者は、勤労契約の形(正社 員、非正規社員など)に関係なく、誰でも請求して使うことができる。
(2) 流産または死産の休暇期間
流産または死産する前に妊娠期間にともなって段階別に保護休暇が付与される。
- 妊娠~11週以内:流産または死産した日から5日まで保護休暇付与
- 妊娠12週~15週以内:流産または死産した日から10日まで保護休暇付与
- 妊娠16週~21週以内: 流産または死産した日から30日まで保護休暇を与える
- 妊娠22週~27週以内: 流産または死産した日から60日まで保護休暇を与える
- 妊娠28週以上: 流産または死産した日から90日まで
(3) 流産または死産休暇給付
- 流産または死産休暇給付は、産前及び産後休暇と同一な基準によって支給される。
- 大手企業は休暇機関のうち最初の60日は会社が、60日を超える30日は雇用保険が支給する(月210万ウォン限度)。
- 優先支援対象企業(中小企業)は休暇期間の90日全て雇用保険が給付を支給する(月210万ウォン限度)。
(4)流産及び死産の休暇給付の申請方法
- 流産・死産休暇給付を受けようとする労働者は、事業主から流産・死産休暇確認書の発給を受け、流産・死産休暇給付申請書と流産・死産の事実を証明する医療機関の診断書とともに、申請人の居住地または事業場の所在地を管轄する雇用センターに提出する必要がある。
03育児休暇
妊娠中の女性労働者や、満8歳以下または小学校2年生以下の子供がいる労働者は、子供の養育のために1年間休職できる。
(1) 適用対象
- 育児休暇は、同じ職場で6ヶ月以上勤続した者のうち、妊娠中の女性労働者や、満8歳以下または小学校2年生以下の子供がいる男女労働者が申請できる。
- 育児問題による退職を防止し、仕事と家庭の両立のために勤労者の身分を維持しながら休職す ることができるように、男女勤労者に育児休暇が保障される。
(2)育児休暇期間
- 育児休暇期間は、最大1年まで保障される。
(3)育児休暇給付
- 育児休暇期間は無給だが、これによって生計に支障をきたすことなく乳幼児を養育することができるように、育児休暇を30日以上使用した労働者に対し、雇用保険から育児休暇給付*を支給している。
- 1ヶ月の通常賃金の80%(上限150万ウォン、下限70万ウォン)
- 生後12ヶ月以内の子供に対して、両親が同時にまたは順次育児休暇を使用する場合、両親それぞれの最初3ヶ月の育児休暇給付として、通常賃金の100%(上限200万~300万ウォン)を支給(3+3両親育児休暇制)
- 母親3ヶ月目+父親3ヶ月目:それぞれ月300万ウォンを上限に支援(通常賃金の100%) 母親2ヶ月目+父親2ヶ月目:それぞれ月250万ウォンを上限に支援(通常賃金の100%) 母親1ヶ月目+父親1ヶ月目:それぞれ月200万ウォンを上限に支援(通常賃金の100%) → 両親それぞれに最大750万ウォンまで支援
- 育児休暇給付とは別に、優先支援対象企業の事業主に対しても、出産育児期雇用安定奨励金として育児休暇支援金(特例*適用時は月200万ウォン、その他は月30万ウォン)が支援される。
- (特例) 生後12ヶ月以内の子供を対象に3ヶ月以上の育児休暇を許可する事業主に対し、最初3ヶ月間、月200万ウォンを支援
(4)育児休暇給付の申請方法
休職する30日前に、事業主に育児休暇申請書を提出する
育児休暇給付を受けようと思う勤労者は事業主から育児休暇確認書の発給を受けて育児休暇 給付申請書と一緒に申請人の居住地または事業所所在地を管轄する雇用センターに提出する。
書類
- 会社から受け取る書類:育児休暇確認書、賃金台帳、勤労契約書の写しなど賃金を確認できる 書類
- 雇用労働部のホームページや雇用センターから受け取る書類:育児休職給付申請書
04育児期の勤労時間短縮
- 満8歳以下または、小学校2年生以下の子どもがいる勤労者は、子育てのために一週間の勤務時 間を15~35時間に減らして勤める育児期の勤労時間短縮ができる。
(1)適用対象
- 育児期の勤労時間短縮は一つの職場で6ヶ月以上ずっと勤めて、満8歳以下の小学校就学前の 子供がいる男女勤労者が申請することができる。
- 育児期勤労時間短縮制度は仕事をしながら育児もできて、勤労者の経歴断絶の防止と業務熟練 度の低下防止、雇用連続性の保障などが可能だ。
(2) 使用期間
- 育児期の勤労時間短縮は期間は最大1年まで保障される。ただし、育児休暇の未使用期間があ れば、その期間を合算して最大2年まで使用できる。
(3)育児期の勤労時間短縮給付
- 育児期の勤労時間短縮期間において、勤労した時間に対しては事業主から賃金が支給され、短縮された勤労時間に対しては雇用保険から育児期の勤労時間短縮給付(1日1時間短縮分:通常賃金の100%(上限・月200万ウォン)、残りの短縮分:通常賃金の80%(上限・月150万ウォン)を基準に、短縮された勤労時間に比例して支給)が支給される。
- 育児期の勤労時間短縮給付とは別に、優先支援対象企業の事業主に対しても、出産育児期雇用安定奨励金として育児期の勤労時間短縮支援金(月30万ウォン、インセンティブ*適用時は月40万ウォン)と代替人材支援金(月80万ウォン、引き継ぎ期間は120万ウォン)が支援される。
- (1号~3号インセンティブ) 事業場の1番目から3番目までの育児期勤労時間短縮者に対して月10万ウォンを追加支援
(4)育児期の勤労時間短縮給付の申請方法
育児期の勤労時間短縮をする30日前に、事業主に育児期の勤労時間短縮を申請する。
育児期の勤労時間短縮給付を受けようと思う勤労者は、事業主から育児期の勤労時間短縮確 認書の発給を受けて育児期の勤労時間短縮給付申請書と一緒に、申請人の居住地または事業 所所在地を管轄する雇用センターに提出する。
書類
- 会社から受け取る書類:育児期の勤労時間短縮確認書、賃金台帳、勤労契約書の写しなど賃金 を確認できる書類
- 雇用労働部のホームページや雇用センターから受け取る書類:育児期の勤労時間短縮給付申請書
- 労働者が妊娠した場合、出産前または出産後に出産前後休暇を取得することができる。また、満8歳以下または小学校2年生以下の子供を養育するために、育児休暇(育児期の勤労時間短縮)制度を利用することもできる(育児休暇の場合は、妊娠中の女性労働者を含む)。
05雇用保険未適用者の出産手当金
(1)事業目的
- 所得活動を行う‘雇用保険未適用者’の出産後の所得減少に対する母性保護と生計支援を目的と して、出産手当金を支援(’19.7.1施行)
(2)支援対象
所得活動を行う1人事業者、特殊雇用職、自由契約者(フリーランサー)、雇用保険受給条件(180 日)未充足者などが支援を受けることができる
- 被雇用人がいない単独、共同事業者(不動産賃貸業を除く)
- 出産前18ヶ月のうち3ヶ月以上所得活動を行った特殊形態の勤労者、フリーランサー
- 雇用保険の適用を受けていない勤労者
雇用保険に加入したが、出産前後休暇給付の受給条件のうち‘被保険単位期間180日’を満たせ ない勤労者
雇用保険法上の適用除外事業の勤労者または雇用保険法適用除外者
雇用保険未成立事業所の未加入勤労者
(3)支援金額と申請時期
- 合計150万ウォンで、出産日から1年以内に申請できる。期限内に申請しない場合は失効する。
(4)雇用保険未適用者の出産手当金の申請方法
- 出産手当金の支給を受けようとする者は、雇用保険ホームページ(www.ei.go.kr)に会員登録し てから申請するか、申請人の居住地または事業所の所在地を管轄する雇用センターを訪問また は郵便で申請できる。
- 必要書類:出産証明書(家族関係証明書)、所得活動証憑資料、事業者登録証明書など
- 雇用センターの担当が、必要な書類以外に出産手当金を支給するために追加証憑書類を要請する場合がある。
06配偶者出産休暇
配偶者が出産した男性労働者は、10日の有給休暇を使用できる。
(1)適用対象
- 配偶者が出産した男性労働者
- 配偶者の出産に対して労働者に休暇を与えることで、配偶者と赤ちゃんの健康を守り、男性の育児参加を拡大することができる。
(2)配偶者出産休暇期間
- 有給休暇10日(ただし、出産した日から90日以内に使用しなければならない。)
(3)配偶者出産休暇給付
- 優先支援対象企業に所属している労働者は、休暇期間中最初の5日に対し、通常賃金の100%(上限額401,910ウォン)を、雇用保険から支給を受けることができる。
- 最初の5日に対して上限額を超える通常賃金と残りの5日の通常賃金は、事業主が支給しなければならない。
(4)配偶者出産休暇給付の申請方法
配偶者出産休暇給付の支給を受けようとする労働者は、事業主から配偶者出産休暇確認書の発行を受け、配偶者出産休暇給付申請書と一緒に申請人の居住地または事業場所在地を管轄する雇用センターに提出する。
必要書類
- 会社から受け取る書類:配偶者出産休暇確認書、賃金台帳、労働契約書の写しなど賃金を確認できる書類
- 雇用労働部のホームページや雇用センターから受け取る書類:配偶者出産休暇給付申請書

この著作物は、“公共ヌリ第4類型:出所表示+商業的利用禁止+変更禁止” の条件に基づいて利用することができます。
Dim
Dim
딤영역
딤영역